令和5年9月定例会一般質問詳細
皆さんこんにちは!桜沢ひろとです。
タイトルのとおり、9月の一般質問での発言と市の答弁の要約を掲載します。
市の答弁の全文、再質問、再答弁については掲載しませんのでご了承ください。
インターネット中継であれば、市の答弁や再質問・再答弁までご確認いただけます。
インターネット中継と以下に掲載する質問や市答弁要約は、正式な記録ではないことにご注意ください。
なお、正式な記録は「羽村会議録検索」で公開されますが、公開まで2カ月程度かかります。
今回は、防災と防犯について質問を行いました。
防災:災害時における衛星通信の活用による通信網の強化や、既存のツールを活用した情報発信等
防犯:地域を見守る目の確保やICT技術を活用した子どもの見守り等
再質問は掲載していませんが、再質問を通じて示した課題に対する前向きな姿勢を見せてもらったこともあり、今後の市の動きを見守りたいと思います。
(以下、黒字が私の発言で青マーカーが市の答弁の要約です。)
櫻沢裕人です。事前の通告に従いまして、2項目質問させていただきます。
1項目めは、「災害時の行政の対応や備えについて」です。
総務省が公表した令和3年版情報通信白書によれば、2016年の熊本地震時にスマートフォンを利用してSNSから情報収集を行う割合は約50%となっており、2011年の東日本大震災時の1%程度から大きく利用率が上昇しました。
現在はスマートフォンの所持率やSNSの利用率が全年代でさらに上昇しているため、災害時におけるSNSからの情報収集を行う割合も上昇すると推察されます。
市は羽村市地域防災計画等を策定し、立川断層帯地震等の様々な災害に備えていますが、他の自治体等の経験と知識、市民や事業者等との綿密な連携、発展した技術の活用等により、市民の生命・身体の安全のさらなる確保が実現できるよう、市の災害に関する対応や備えについて伺います。
質問(1)災害時に利用可能な通信網の整備や活用について
①市は多摩ケーブルネットワーク株式会社と地域広帯域移動無線アクセスシステム通信網の整備に関する協定を締結し、災害時に避難所で利用できる公衆無線LANサービス「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」の運用を開始していますが、各避難所に集まる数百人の避難者が同時にインターネット接続することは難しいと聞いています。
そこで、公衆無線LANサービスの同時接続可能な端末数、通信速度、及び災害時における具体的な運用方法を伺います。
→同時接続可能なスマートフォン等の端末数は200台程度で、通信速度はデータ通信量により変化するが、平均速度50Mbps程度の性能の機器を全体で共有することとなる。
データ通信量の大きい動画視聴や画像の送信等を避け、状況に応じて譲り合って利用していただくなど、利用時の注意事項等について避難所への掲示等で周知し、混乱なく利用されるよう対応していく。
②衛星通信について国の防災基本計画では、「地域衛星通信ネットワーク等の耐災害性に優れている衛星系ネットワークについて、国、都道府県、市町村、消防本部等を通じた一体的な整備を図る」とされています。そこで、
ア 平成17年第5回定例会において、市は自治体衛星通信機構が提供する地域衛星通信ネットワークへ加入している旨の答弁がありましたが、現在も加入しているでしょうか。
→地域衛星通信ネットワークとは、災害発生時に停電や断線により地上の通信網が使用できなくなる事態に備え、衛星通信回線を用いて全国の自治体や防災関係機関相互で情報伝達を行うための広域ネットワークである。
地域衛星通信ネットワークは、都道府県と市区町村を結ぶ防災行政無線の衛星系として位置付けられている。
市が災害発生時にこのネットワークを利用する場合は、東京都に設置されている地域衛星通信ネットワークの地球局を通じて利用することとなる。
このネットワークは、市と東京都との間で整備されている東京都防災行政無線の仕組みの中に組み込まれているため、現在も地域衛星通信ネットワークを利用した情報伝達が可能。
イ 耐災害性に優れた衛星系ネットワークについて、市はどのように整備を進めているでしょうか。
→耐災害性に優れている衛星通信ネットワークは、従来と比べて高性能かつ低コストな、いわゆる第3世代システムが、既に東京都において整備されており、 市区町村においては、東京都防災行政無線を通じて第3世代の衛星通信ネットワークを利用することができることから、市が独自で整備をする必要はないものと捉えている。
ウ 市の既存の通信設備が災害により使用できなくなった場合でも、災害の初動対応の遅滞防止、市のホームページやSNS等を活用した迅速な情報発信等が可能となるよう、民間企業等の衛星通信サービスを用いてインターネット回線を冗長化してはいかがでしょうか。
→災害時に、インターネット回線に接続できなくなる場合に備え、別の通信手段を確保しておくことは重要であると考えている。
サービス内容やネットワークの構成、費用など、今後、詳しい内容について情報収集する。
③SNSアプリ「LINE」の活用について
SNSの中でもLINEは他のSNSと比較して全年代での利用率が圧倒的に高いため、平時・非常時を問わず多くの自治体が業務にLINEを活用しています。
また、LINEと外部システムを連携させて災害時の対応を円滑化している事例もあります。そこで、
ア 市ではアプリ「Yahoo!防災速報」やメール配信サービスを活用した防災情報等の発信を行っているとのことですが、令和5年度運用開始予定のLINEの市公式アカウントでも、Lアラート(災害情報共有システム)と連携して災害時の情報発信を行ってはいかがでしょうか。
→Lアラートとの連携による災害時の情報発信については、今後LINEに組み込むシステムの提供事業者を選定していく中で、Lアラートとの情報連携が可能かどうか確認し、検討していく。
イ LINEを活用して避難所における避難者の受付や炊き出しや物資の到着時間を通知するシステムを導入している自治体があります。市においても、災害時にインターネット接続が可能な通信環境を整備することで同様のシステムを導入できると思いますが、検討してはいかがでしょうか。
→災害時における避難所の状況や物資の配布に関する情報などは、市民の皆様へ広く周知する必要があることから、LINEを活用した情報発信について、検討していく。
次に、質問の第2項目め、「市民の安全について」についてです。
令和2年度羽村市市政世論調査報告書では、希望する将来の市のまちづくりとして一番目に「防災・防犯や交通安全に配慮した安心して暮らせるまち」、二番目に「高齢の方や障害のある方が住みなれた地域で安心して暮らせるまち」が多く挙げられています。
都内や市内の犯罪件数は近年低下傾向にありますが、警視庁が公表している市内で発生した前兆事案は、依然として市民の目を引き不安を感じさせています。
誰もが安心して暮らせるまちと思えるよう、これまでの関係機関や地域の方等の協力に加え、新たな技術を積極的に活用し、地域の目を増やしていくことも重要であると考えますので、市の今後の方針や対応について伺います。
質問(1) 市の前兆事案や犯罪への対応について
① 平成30年以降の市内の声掛けやつきまとい等の前兆事案の発生件数と、近年の前兆事案の発生状況に関する市の見解を伺います。
→平成30年が42件、令和元年が43件、令和2年が26件、令和3年が30件、令和4年が24件。
減少傾向にはあるものの、依然として発生しており、引き続き注意喚起を行っていく必要があると考えている。
② 現在、市、関係機関、事業者、市民等が連携して地域の安全を守っていますが、今後は人口減少、高齢化等の様々な社会構造の変化により、前兆事案や犯罪の防止に効果的である地域の目の力が弱まっていく可能性があります。市は今後地域の目をどのように確保していくのでしょうか。
→NPO法人市民パトロールセンタ―はむらと連携して市内全域の防犯パトロールを実施しているほか、防犯関係団体や町内会・自治会による市民パトロール、PTA、学校関係者、ボランティア等による児童の登下校時の見守り活動などが実施されている。
市では、防犯・交通安全及び火災予防推進会議を開催し、関係団体との連携強化を図るとともに、毎年12月には年末防犯・交通安全・火災予防パトロール週間を設定し、市民の皆様による市内全域でのパトロールを実施している。
引き続き、関係者の皆様と緊密に連携し、地域の目を確保し、防犯対策を推進していく。
なお、地域の目を補完する機能として、防犯カメラの設置も有効な手段であることから、市では、これまでに計47台の防犯カメラを設置してきた。
今後も福生警察署の意見を聴きながら、必要性が高い場所への防犯カメラの設置を検討していく。
(2) ビーコンを活用した市民の安全確保について
① 栄小学校ではPTAの主導によりICタグを利用した児童の登下校の確認ができるサービスを導入していると聞いています。そこで、
ア サービスの導入について保護者や関係者からはどのような声があるでしょうか。
→「無事に登校したことが分かって、安心できる」、「子供の帰宅時刻を予測して、家に帰ることができる」等の声がある。
イ 市内の他の小学校では、栄小学校と同様のサービスの導入について検討が行われているでしょうか。
→同様のサービスの導入について検討している小学校は、現時点ではない。
② 他の自治体では民間事業者とともに、ビーコンを持った児童が通学路上の固定基地局や見守りに協力してくれる市民等の近くを通過すると保護者に児童の居場所が通知される「見守りサービス」を実施しているところがあります。このようなサービスは、児童の通学路上の見守りの強化にとどまらず、高齢者等の見守り、位置情報データを活用し社会課題を解決するスマートシティの実現等、様々な場面で活用可能であるため、全庁横断でサービスを導入している自治体もあります。そこで、誰もが安心して暮らせるまちとなるよう、市でも全庁を挙げて「見守りサービス」の導入を進めてはいかがでしょうか。
→ビーコンを活用した見守りサービスについては、ICTを活用し子どもや高齢者の見守りをサポートするものであり、導入している自治体があることは承知している。
全庁的な「見守りサービス」の導入については、今後他自治体での導入事例を情報収集し、活用方法や有効性等について調査・研究していく。

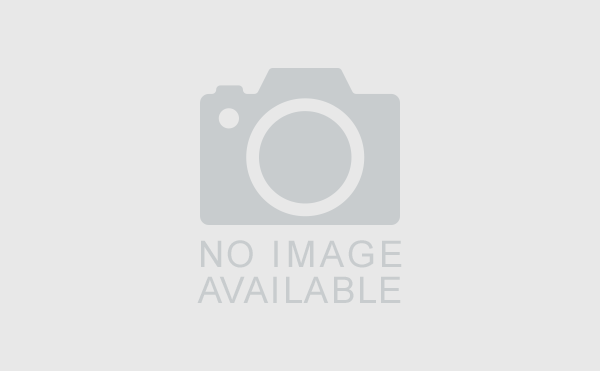
災害や犯罪は、経験してはじめてその備えの大切さに気付きがちであり、経験してしまってからでは後悔先に立たず、といったものでしょう。私達は、身近に起きた災害や犯罪に目を向け、自分にも起こり得ることとして意識することが必要です。
引き続き防犯、防災策とセットで情報や提案を発信、啓蒙いただければ幸いです。